『失敗の本質』名著から資産運用戦略を考える
『失敗の本質』、組織論や戦略論に関する名著で、日本を代表する企業の経営者からも指示されている本なので、読んだ事がある方も多いと思いますし、昨年末に新装版が発売されましたね。
私も学生時代に読みましたが、その時は組織に属して動く経験がまだ少なかったので、面白いけど腹落ちするまでは行かなかったように記憶しています.
サラリーパーソンとして15年以上経ち、組織の一員として働くことにすっかり馴染んでしまった身として、読み直したら学びがあるかも期待して本棚から引っ張り出して読んでみると、「これ、投資や資産運用の戦略をどう考えるかのヒントが満載だな」という気付きがあったのでこの記事でまとめてみました.
価値観のベクトルを揃える
「本部の人間は現場を何も分かっていない」と現場が文句を言い,一方で「現場の人間は本部の言う事を全く聞かない」と本部が非難するという「本部 vs 現場」という構図は組織論の典型ですが,太平洋戦争時の日本軍がまさにこれで,大本営と現場のベクトルがバラバラだったそうです.
一方,米軍の将校は,参謀と散歩をしてその中で議論を重ねたり,普段から価値観の統一を図っていて,これが指揮系統と現場のスムーズな意思疎通に役立ち,いい結果をもたらしたというのが本書の考察です.
資産運用も同じで,資産運用は長期で取り組むプロジェクトなので、家族間で価値観が一致していないと、「なんで5年も10年も我慢して積立をしなければならないのか」といういざこざが生じてしまうので,家族で価値観と目指す姿のベクトルを揃えておくのは大事だなと感じました.
投資戦略は帰納と演繹の循環で策定すべし
戦略策定には帰納と演繹の循環が必要で,帰納だけでは論理破綻の可能性がありますし,演繹だけでは机上の空論かもしれません.
日本軍の戦略立案は帰納的側面が強く,それ自体は悪いことではないものの、日本軍の戦略策定は原理や論理に基づくよりも、情緒や空気に支配され、事実から法則を析出するという本来の意味の帰納法ではありませんでした.
これを読んだ時,マーケットの動きに一喜一憂し、メディアやSNSが不安や狂乱を駆り立てる今の状況が思い浮かびました.
本来なら「この状況から何を学ぶべきか」「過去の事例やセオリも考えて,どう行動するか」を考えるべきですが、特にSNSはそれと程遠いので,こうしたノイズとの距離間を自分の中で決めておくことが大事になってきます.
投資戦略はアップデートし続けるもの
どんな状況でもワークするような投資戦略を知りたい,というのは誰もが思うところですが,この本を読むと残念ながらどんな状況でもワークし,万人に当てはまる投資戦略なんて都合のいいものはないとわかります.
戦略は状況の変化に応じてアップデートすべきであり、その中で様々な変化が生じるが、その中から有効なものを採用していくというサイクルを回し続けることが必要だと書かれていて,資産運用も一緒ですね.
たとえば,ゼロ金利政策が適用されていた時なら,ローンで資金を調達して高い利回りが期待できる投資に回すというのがセオリーでしたが,金利が上がり始め,しかもそのトレンドは続くだろうと考えられている今,その戦略は書き直さなければいけません.
アップデートすべきもの(戦略、戦術)と,すべきでないもの(価値観)を見極め,必要なものには定期的なアップデートを加えていこうと思います.
投資に直接関係しない本でも,投資家の視点で読んでみると色々な発見があって面白いですね.

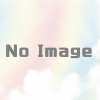






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません